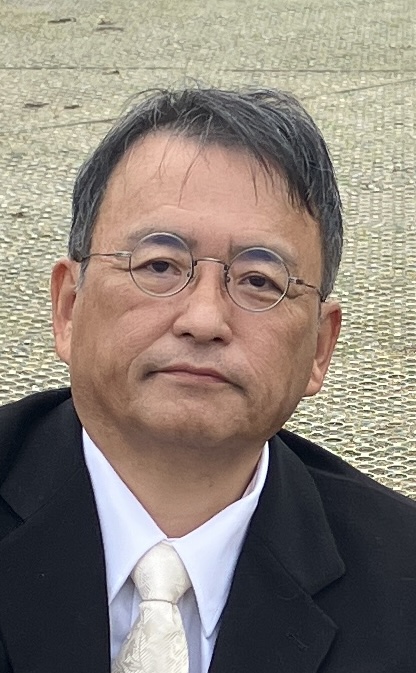
元旦に発生した能登地震。本当に大変だなぁと感じ、少しずつ地域のインフラが復旧されていく様子を知る度に頑張っているなぁと陰ながら応援していたのですが…
梅雨の終わりや夏の終わりなど季節の移り目には大きな気象災害が起きますね。今回の能登の豪雨被災は酷すぎます。
心が折れると住民が話していましたが、本当に…。 地震での人口減少に加えて、豪雨水害で更に過疎が加速しそうで心配ですが、地域の方々が一日も早く明日に希望を持てる日が来ることを願っています。
猛烈な暑さの夏がやっと退場し、季節が秋色になりつつありますが、台風など来ないように願っています。 あまりに暑すぎて園庭遊びが出来ませんでしたが、暑さが少し落ち着いたので、園庭に日除けシートを増設し運動会練習も本格的になり、園庭に子ども達の姿が戻ってやっと保育園らしくなりました。
十月は運動会だけで無く修園旅行や中学生が来園する体験学習や大避難訓練など行事も沢山。 先月に引き続き、学研の科学学習教室も開催予定です。 さらに県の保育所監査も行われる予定で、忙しい月になりますので、張り切って取り組むつもりです。
さて、先日NHKで面白い番組を観ました。「百聞は実験に如かず」というもので、子どもの発達とウソについての実験番組でした。
もう随分前の事ですが、保護者に園での出来事をお話しすると、子どもの言っている事とちがう、家の子は嘘をつかない… 先生は我が子が嘘つきだとおっしゃるのですか。と言われて、 ええ子どもはしっかりウソをつきますと答えた事を思い出しました。
番組では、年中児と年長児で動物の鳴き声を当てるクイズを行っていました。 まず、犬や猫などの鳴き声を流して園児に当てさせる。正解すると後ろに隠していた犬や猫のぬいぐるみを見せながら大げさに褒める。
次に、聞いたことが無い電子音を鳴らすが、問題の途中で出題者は電話だと呼び出される。出題者は子どもに後ろを見ないように約束してその場からいなくなる。でも、子どもは振り向いてぬいぐるみを確認してしまう。ぬいぐるみはキリン。
出題者が帰ってきて答えを聞くと、子どもは「思い出したキリンだ」と答えたり、前に動物園で聞いたことがあるなど、それらしい事を付け加えながら回答していました。 年齢が上がるほど回答にそれらしい説明をつけていました。
十人ほど実験したが、言いつけ通り振り返らず答えられない子は1人だけでした。判らない事を探求したい気持ちと、褒められたい気持ちが約束を破る行動につながっているのだと、子どもの心理がよくわかる実験番組でした。
3歳未満の子どもでは約束も出来ないし、嘘もつけない。我が子が嘘をついたという負の感情よりも嘘をつけるようになったと成長を喜ぶべきかもしれませんね。
自己の利益や他人を陥れる嘘はいただけませんが、他の人を思いやっての嘘をつくことはありますよね。子ども達の心理面をじっくり考えながら保育できる環境でありたいと願っています。
運動会は天候に恵まれる事を願っています。
|

